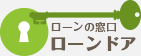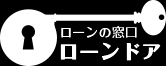住宅の購入を考えている方の中には「今後の住宅ローン金利はどのように推移するのか」と気にしている方も多いのではないでしょうか。日銀がマイナス金利政策を解除したことにより、市場全体で金利が上昇し始めました。2025年以降も更なる上昇の可能性があります。住宅ローン金利も引き上げの対象であり、借り入れコストが継続的に上昇すると予想されています。
住宅ローンを組む際には、金利の動向を見極めるとともに、金利を左右するさまざまな要因に関する知識を身につけながら金融機関を比較検討することが重要です。本記事では、住宅ローンの推移予想や金利の種類、金利以外に押さえておきたい住宅ローン選びのポイント3点について解説します。
住宅ローン金利の現在までの流れ
上昇し始めた住宅ローンの金利は、今後、どうなっていくのでしょうか。長年続いてきた低金利時代の先を推し量るには、これまでの住宅ローンにおける金利の推移を知ることが大切です。
低金利時代
長く続いている低金利時代の先を推し量るには、これまでの住宅ローンにおける金利の推移を確認することから始めましょう。ここでは、低金利が続いた時代の住宅ローンの金利動向を変動金利・固定金利に分けて解説します。
変動金利
住宅ローンの変動金利の水準は、2009年ごろから現在まで変わらず、基準金利は、2.475%を維持されてきました。しかし、現在は転換期を迎えています。2024年10月から、多くの金融機関では変動金利の基準金利を年2.625%に改定しました。
固定金利
1991年頃、旧住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)の固定金利は5%台で推移していました。しかしバブル経済の崩壊により、日本経済が不況に陥ったことで、1990年代末には2%台まで低下しました。2008年のリーマンショック後の2009年5月頃には約4%まで上昇しましたが、その後は再び下落して現在に至ります。
【2024年3月】日銀はマイナス金利政策の解除を発表
2024年3月の金融政策決定会合において、日銀はマイナス金利政策を終了することを正式に発表しました。日銀の当座預金の金利を0.1%に設定し、これにともない、日銀は各金融機関へ、短期市場で資金を貸し借りする際の無担保コールレートの金利を0~0.1%の範囲で推移するように働きかけをすることになりました。
また、日銀はCP(Commercial Paper)等および社債等について、買入れ額を段階的に減額し1年後をめどに買入れを終了すると発表。これにより市場への資金供給の抑制を図ります。ただし、長期金利が急激に上昇する場合には、毎月の買入れ予定額にかかわらず、機動的な買入れ額の増額、日銀があらかじめ決めた利回りで金融機関から無制限に国債を買い入れる指値オペによる市場操作を実施するなどとしています。
日銀の金利政策の解除が発表された理由とは?
日銀による利上げは、2007年2月以来約17年振りとなりました。日本の景気は、一部弱めの動きもみられますが、金と物価の好循環の強まりが確認されています。日銀は、「展望レポート(経済・物価情勢の展望)」の見通し期間終盤にかけて、2%の物価安定の目標が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断された」としています。これにより、マイナス金利政策などの金融緩和策が役割を終えたと見なされたため金融政策の解除に至ったわけです。
【2024年12月】住宅ローンの金利相場
住宅金融支援機構が発表する2024年12月現在の新機構団信付きのフラット35等の借入金利水準は次のとおりです。
- 融資率 9割以下の場合:もっとも多い金融機関の金利は2.04%
- 融資率 9割以上の場合:もっとも多い金融機関の金利は2.15%
「イー・ローン」のデータベースから2024年12月 の住宅ローンの金利相場は次のとおりです。
- 変動金利:イー・ローン掲載商品の12月の変動金利の最低金利は0.3%
- 固定金利:イー・ローン掲載商品の12月の固定金利の最低金利は、固定3年は0.800% 、固定5年は0.850% 、固定10年は0.700%
今後の金利の推移について予想
マイナス金利政策の解除後、金融機関が金利を引き上げる動きが出てきました。特に、変動金利に影響を与える「短期プライムレート」は2009年1月13日以降、ずっと変化はありませんでしたが、2024年7月に開かれた金融政策決定会合により、政策金利を0.1%程度から0.25%程度に引き上げると決定したことで多くの銀行が追従しました。追加利上げは物価や経済の見通しにそって推移しているものの、輸入物価が再度上昇に転じてきており、物価の上振れリスクに注意する状況をふまえ、金融緩和の度合い調整が適切であると判断したためです。とはいえ、利上げをしても低い水準での調整になるため、景気に大きな影響を与えることはないとしています。
住宅ローンの金利の種類

住宅ローンの金利の種類は大きく分けて3種類です。それぞれについて見ていきましょう。
住宅ローンの金利の種類
全期間固定型
長期的な返済プランを立てて、金利上昇リスクに備えて返済金額を確定したいと考える方におすすめです。全期間固定金利は、その名の通り返済が終わるまで金利は固定され、途中で変わることはありません。長期間の返済額が確定するため資金計画を立てやすく、金利上昇リスクをヘッジできます。ただし、固定金利は変動金利よりも金利が高くなるため、市場金利が低下局面では支払利息が変動金利よりも多くなることがデメリットです。
固定金利選択型
一定期間を経過したのちに金利の見直しが可能なタイプの金利です。安定した返済計画を考えつつも、金利動向も見極めて対応したいと考える方におすすめです。「3年」「5年」「10年」「20年」というように一定の固定期間を選択することが可能で、固定期間選択中は返済額が変わりません。固定金利期間終了時には再度金利タイプを選択できます。原則固定期間選択中は、金利タイプを変更できません。低金利の状況下では返済額を確定したうえで低金利のメリットを享受できる半面、借入後金利が上昇した場合、初めから固定金利にしておいたほうがお得になる場合があります。
変動金利型
低金利の金利情勢を最大に生かしたいと考える方におすすめです。金融機関独自に短期プライムレートに連動する一定の基準によって金利を決定し、年に2回基準金利の見直しをするのが一般的です。金利変更があっても5年間は返済額が変わりません(5年ルール)。5年ごとに返済額の見直しを行いますが、変更時は変更前返済額の1.25倍の範囲内で変更されます(1.25倍ルール)。金利が下がったときは金利低下のメリットを享受できますが、金利が上昇すると総返済額が増加します。
金利のシミュレーション
金利が異なることで、月々の支払い、支払総額、支払利息がどれだけ変わってくるのかを具体的に見ていきます。
| 金利 | 毎月の支払金額(円) | 支払総額(円) | 利息の支払総額(円) |
|---|---|---|---|
| 0.5% | 10万6,401円 | 3,192万300円 | 192万300円 |
| 1.0% | 11万3,062円 | 3,391万8,600円 | 391万8,600円 |
| 1.5% | 11万9,981円 | 3,599万4,300円 | 599万4,300円 |
※本シミュレーションは「イー・ローン」の「住宅ローンのかんたん返済額シミュレーション」により計算してあります。
住宅ローンは、金額も大きく返済期間も長期に及びます。たった0.5%の金利の違いで、毎月の支払金額は約6,000円~7,000円、支払総額と利息の支払総額は約200万円もの差ができることに驚く方もいるのではないでしょうか。
変動金利の場合は、低金利の情勢が続き金利に変更がなければ大きなメリットが得られることが分かります。しかし、金利が上昇した場合には毎月の支払金額が増えるので、完済までの支払総額も増加します。それぞれの金利と毎月の支払金額、支払総額を比べるとわかるように、当初変動金利で借り入れしたときの金利(0.5%)が返済途中に上昇して固定金利(1.0%)を上回れば、場合によって完済までの支払総額が逆転する可能性も考えられます。
金利だけじゃない住宅ローン選びのポイント
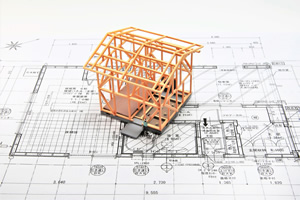
住宅ローンの選び方のポイント
付帯保障について
- 全疾病保障
8疾病(ガン、急性心筋梗塞、脳卒中、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎)と8疾病以外の病気やけがにより働けなくなったときに月々の返済額を保障する全疾病保障を付保する。 - がん診断保険金特約
「がん」と診断されればローン残高が0円になる特約を付保する。がんが治った後も住宅ローンの返済が再開することがない。
住宅ローン借り入れの際は団体信用生命保険の加入が条件となっていることが多く、通常の団体信用生命保険は、住宅ローンの返済期間中に死亡・高度障害・または治療の効果がない重度のガンと診断された場合に、保険金によって住宅ローンが返済され、残された家族が返済を負担することがないようになっています。通常の団体信用生命保険のほかに付帯保証を付ける金融機関も多くあります。
他にも「3大疾病特約」「7大疾病特約」などさまざまな疾病特約を付保する金融機関があるので、付帯保証の有無によって住宅ローンを選ぶことも1つの方法です。保険料を金融機関が負担するケース、別途保険料を支払う必要があるケースと金融機関によって異なりますが、万が一のときに残された家族のためにも、ぜひ検討してみてください。
借入先
キャンペーンや取引実績に応じて金利を引き下げる金融機関が多いことを忘れてはいけません。以下のような条件がポイントとなります。わずかな金利の差でも大きな違いが出る住宅ローンだからこそ、お得な住宅ローンも見逃さずに探したいものです。
- 給与振り込みを利用している
- 同じ金融機関でカードローンなどの利用実績がある
- 期間限定のキャンペーンを行っている
- Web利用による申込み
保証料や手数料などの諸費用
住宅ローンには諸費用がかかります。事務取扱手数料は定額型で3万円前後 、定率型では借入金額の1%~2%程度かかる金融機関が多いです。保証料や保証会社への事務手数料がかかることもあります。また、金利のタイプも変更するごとに1万円前後の手数料がかかるのが一般的です。その他、一部繰上返済・繰上完済をするにも手数料がかかる場合があります。
インターネットで手続きすると手数料が無料になったり安くなったりする金融機関、借入後10年を経過すると繰上完済手数料が無料になる金融機関など手数料もさまざまです。手数料とはいっても金額は決して少なくないため、軽視できません。金利以外にも手数料や利便性にも目を向けて住宅ローンを選ぶようにしましょう。
住宅ローンを比較検討するなら「イー・ローン」
日銀によるマイナス金利政策解除や長期国債買入れ額減少にともない、変動金利・固定金利はともに上昇傾向となることが予想されます。一方で、各金融機関が短期間に極端な金利引き上げを行うとは考えにくいため、住宅ローン利用者に、いきなり負担が重くのしかかる可能性は低いといえるでしょう。
住宅ローンの金利変動は、多くの金融機関が似た動きを見せる傾向がありますが、同じだけ金利が引き上げられるとは限りません。今後住宅ローンの利用を検討する際には、金利動向に注目しつつ複数の金融機関を比較検討することが大切です。
住宅ローンの利用に関する情報をもっと知りたい方は、ぜひイー・ローンのページもご覧ください。
文/手塚 裕之